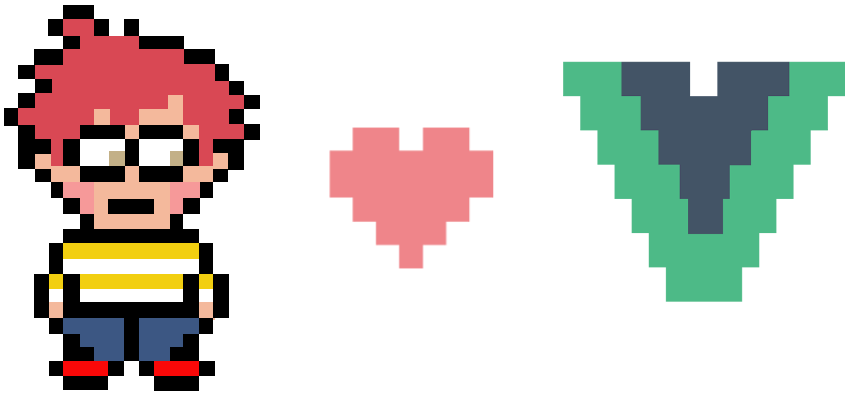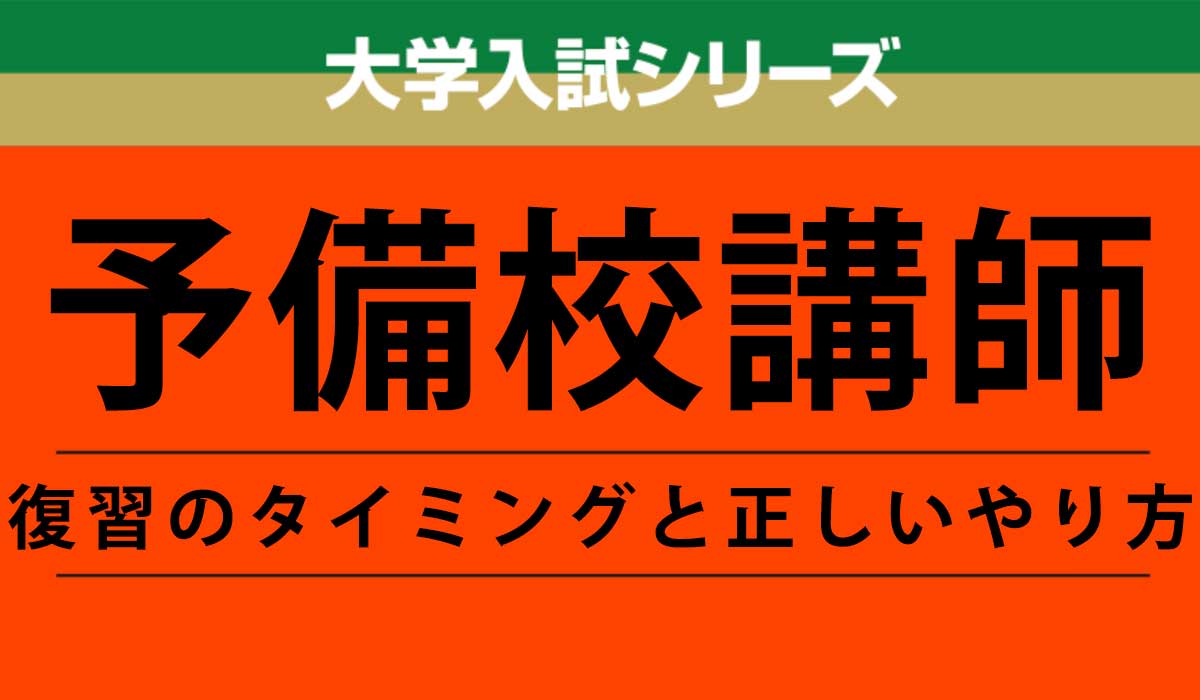大学受験の塾や予備校の数学の授業の時短できる予習方法
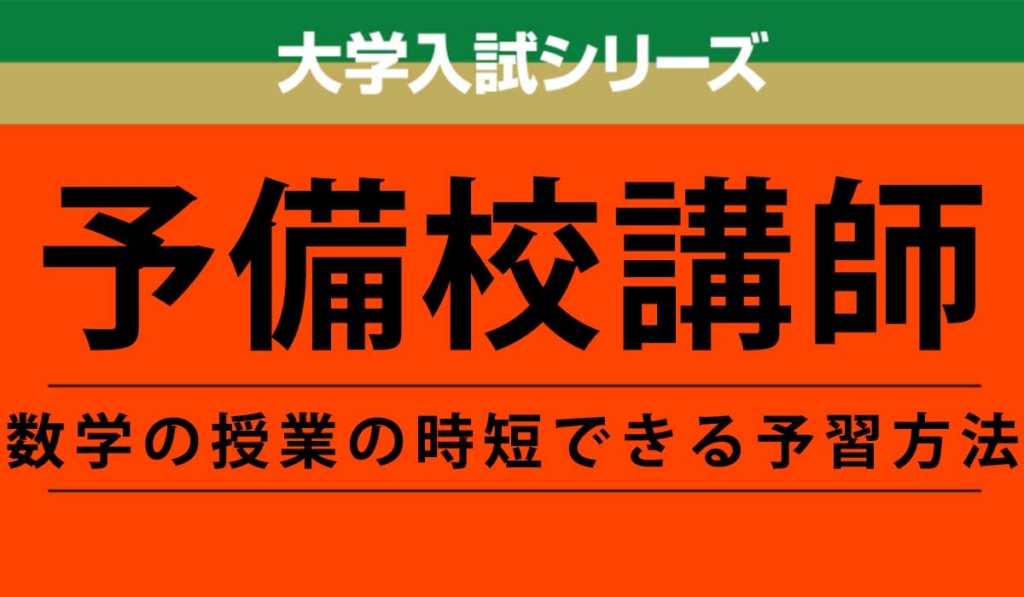
650 回閲覧されました
みなさんこんにちは、jonioです。
大学受験(でなくても)授業を受ける時に予習しなくてもいいと言われない限り予習は絶対にしないといけません。
でも大学受験の場合勉強する科目が多いので予習の時間が限られます。
だから予習の重要性と効率がいい予習のやり方を説明します。
問題を解けなくてもいい
成績が伸びなかった時は完全に復習型で偏差値が40位からスタートしてずっと同じままでした。
そして浪人の時に同じ授業を受けて予習をしたら成績が伸びました。
最終的に偏差値が68.2になりました。
ですので問題を解けなくてもいいので予習はしないと成績は伸びません。
私の授業では予習をしなくてもいいようにその場で解かせることがほとんどですがたまに予習の指示をすることがあります。
受験に受からない、成績が伸びない人は色々理由をつけて予習しません。
私もでしたが大体の人は予習する人はなぜか成績が伸びます。
予習は考える力を付ける練習
予習は解けることを目的にしていなく考える練習だと思っています、予習の段階で問題を全部解けるなら授業の意味がないので。
だから予習は問題を解けても解けなくてもいいから絶対にしましょう。
予習の仕方
では数学の予習のやり方ですが私はこうやってました。
- 問題文を読んで解き方を考えて10分以内に解答が書けるかもと思ったら解答が書ける所まで書く
- 問題文を読んで解き方が全く分からなかったら5分位考えて駄目そうなら次の問題に移る
授業は毎日色んな科目があるので1教科に凄く時間をかける事ができないはずです。
だから↑のやり方で大丈夫です。
これは極力避けた方がいいのですが問題を解く時間がどうしてもなかったら問題文を読むだけでもしましょう。
ちなみに私が受けていた授業の問題は難しすぎて全然解けないので5分位考え次の問題に移ってました。
それでも成績が上がったので長い時間かけて考えなくても大丈夫だと思います。
これを生徒に言うと「先生が賢いからじゃないですか?」と言われる時がありますが私は賢くありません。
予習に凄く力を入れる必要はない
生徒から予習と復習はどっちに力を入れるべきかよく聞かれますが学校、集団、少人数授業でも予習復習共に凄く力を入れなくていいと思います。
学校の授業で黒板に書かないといけなくて問題を解けないと先生がうるさい時は予習に力を入れた方がいいです。
高校の授業は特に初めて見る分野の予習ってちゃんとやるのは無理だしそれができるなら学校の授業を受けなくて大丈夫です。
「へ〜こんな内容なんだ〜」って思う位でいいです。
本来学校の先生がちゃんと説明しないといけないですし予習、復習をするのは数学だけではないので。
習った内容を忘れないようにするのが目的で授業があった日に力を入れて復習しても忘れたら意味がないですから。
私が受験生の時にやった方法を詳しく説明しています。
予習のやり方のまとめ
予習は絶対にしましょう。(予習の必要がない授業は話が別ですが)
現役生、浪人生の時に成績が伸びなくて苦労しているのを私が身を持って経験しているので成績が伸びなかった私と同じになって欲しくないです。
受験勉強はやり方次第で大きく変わります。