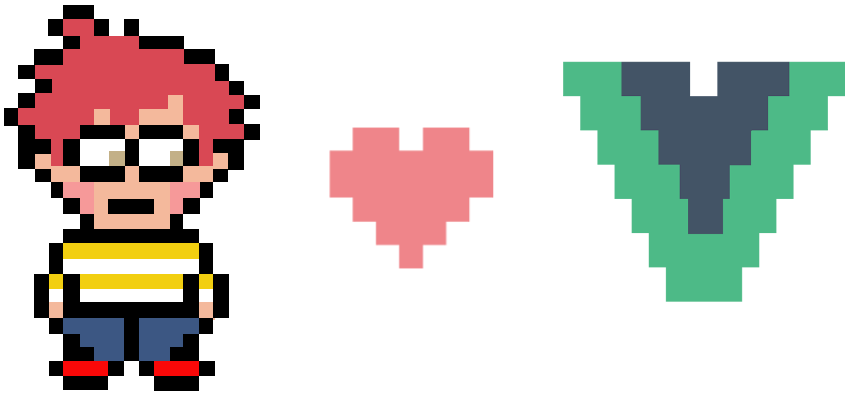完全版。獨協医科大学医学部の数学を対策するための方法
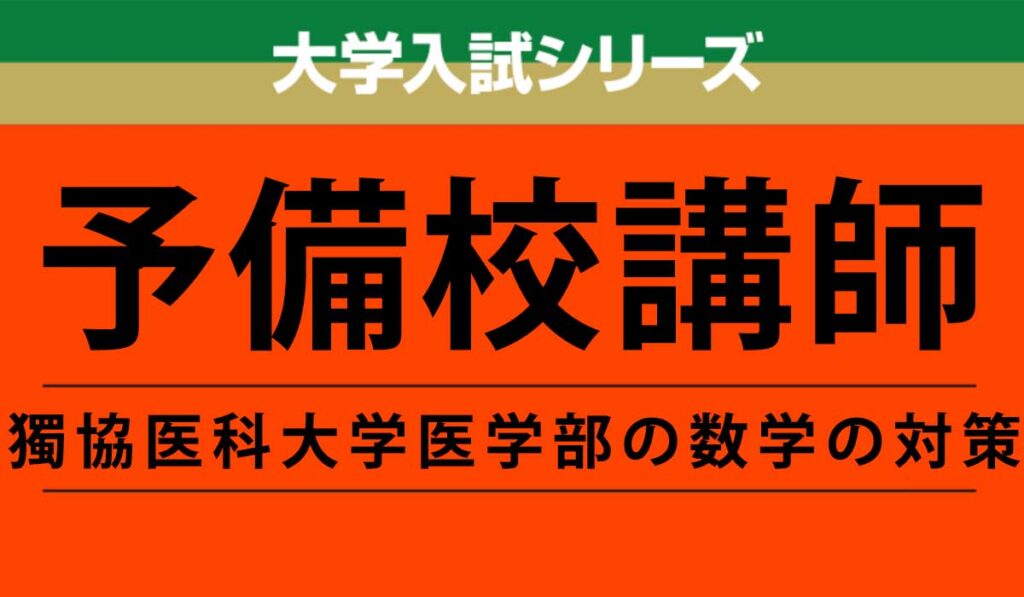
601 回閲覧されました
みなさんこんにちは、jonioです。
医学部受験予備校に行ってなかったら表向きの情報しかネットにはないので対策のしようがないですよね、、
行ってても自分から聞かないと情報を教えてくれない先生もいて私が教える事もあります。
情報は少しでも多い方がいいので獨協医科大学の私なりの対策方法の説明をします。
この記事を見ることで医学部受験予備校に行かなくてよく他のサイトで獨協医科大学の対策を調べなくてもいいように私なりに細かく内容を書きます。
私は講師を辞めていますが講師をしていた時に授業で生徒に伝えていた方法を解説します。
2015年〜2019年の問題を見て説明をします。
目次
獨協医科大学の問題構成
- 満点:200点
- 大問数:5題
- 試験時間:70分
- 解答方法:マークシート
- 大問数:大問1は(1)(2)で大問2〜大問5の中の問題数は変動
問題の特徴
解き方を覚えていないと解けない問題が割と出るので黄色チャートやFocus Goldなどで解き方を覚えないといけないです。
解き方が決まっている問題は医学部ではない学科でよく出る問題(パターン問題)が出ている印象です。
こういうのは私立医学部ではほとんどないので珍しいです。
大問2が確率で大問3がベクトルに固定されています。
大問5は数学Ⅲの定積分が多い印象です。
関数方程式、弧長を求める、回転体の体積を求めるなどです。
問題の感じですが埼玉医科大学が割と似ている感じがします。
試験時間が70分ですが大問が5つあるので試験時間内に全部解くのは恐らく無理です。
今のままの難易度が続けば問題集だと黄色チャートならコンパス4、Focus Goldなら星4まで解ければ対応できると思います。
2019年の問題の難易度の分析
大問1
(1)指数関数、対数関数が出ていますが難易度は簡単です。
(2)複素数平面が出題されていますが難易度は標準的です。
大問2
確率漸化式が出題されています。
色んな大学で出題されていますが黄色チャートにも類題があります。
解き方を知っていれば難しくないです。
大問3
ベクトルが出題されていますが難易度は標準的です。
2つの直線上の点の距離が最小になる時を考える問題の類題がチョイスにあります。
大問4
数学Ⅲの微分と極限を混ぜた問題が出題されています。
難易度は標準的です。
「微分可能→連続」を使う問題が出題されていますが入試ではほとんど使わない印象です。
黄色チャートに類題があります。
大問5
共通接線がある時の問題と面接、 回転体の体積を求める問題と孤の長さを求める問題が出題されています。
難易度は簡単です。
総評価
解きやすい問題が多かったはずです。
計算量が多すぎるので計算力を付けないといけないです。
必要な得点率
点数が公開されていないのですが数学は点数が相当高いはずです。
75%は取らないと合格点にならないと思います。
浪人に寛容か?
寛容かそうでないかがわかりません。
2019年の入学者の現浪比は↓です。
- 現役:20.1%
- 一浪以上:79.9%
となっていて1浪以上がまとめられているからです。
どの順番に問題を解くかと時間配分
塾や予備校に行ってない高校生や集団授業を受けている浪人生は問題を解く時に最初から解いてないでしょうか?
もししてたらよくないやり方です。
理由は私立医学部の場合は入試の問題でよく知られている解き方だけど試験時間的に解かない方がよかったりやたら複雑な問題は捨てないと試験時間内に合格点を取れなくなるからです。
最初から捨てる問題の時もあります。
最初から解いていきなり捨てる問題だったら解くのが大変だったり解けなくて凄く焦るはずです、、
その状態で問題を解けても解けなくてももやもやした状態で次の問題を解いて冷静な状態で解けるでしょうか?
恐らく無理でしょう、、
だから問題を解くときは↓としましょう。
自分にとって解きやすいかもと思う問題から解くといいです。
そうすると気持ちが落ち着いて問題を解くことができて試験時間が終わり合格点を取ることができることができるかもしれません。
私が最初に解かない方がいいと思う分野は整数問題、図形問題、確率、場合の数、データの分析などの思いつかないと解けない分野です。
理由は試験の開始直後は緊張しているので思いつかないかもしれないからです。
大問の最後の問は一旦解かずに次の大問に移りましょう。
大問の最後の問より次の大問の(1)が簡単だからです。
時間配分は考えず試験時間全部を使って問題を解けるだけ解けばいいです。
ちなみに見直しの時間はないです。
大学の過去問を使って問題の解き方の練習をしないといけない
捨てる問題を見極める練習や計算用紙の使い方の練習は過去問を使ってすれば実戦形式なので効果的です。
捨てる問題を見極める練習は必ずしないといけません。
本来捨てるべき問題を捨てずに無理に解こうとすると時間が足りなくなって合格点を取ることができなくなるかもしれないからです。
以下の大学の過去問を使って練習するのをお勧めします!
問題が変に難しすぎる大学は省きます。
東海大学はマークシートなので記述の大学は含みません、対策の記事のリンクもありますのでよかったらご覧ください。
- 川崎医科大学(2018年、2019年が対応している)
- 埼玉医科大学
- 久留米大学
です。
過去問を解く時は必ず解答時間内に解き計算用紙に計算をしましょう。
練習している時に合格最低点の%を取れなくても本番では自分に合った問題が出題されて合格最低点を超える人もいますので諦めずに勉強しましょう。