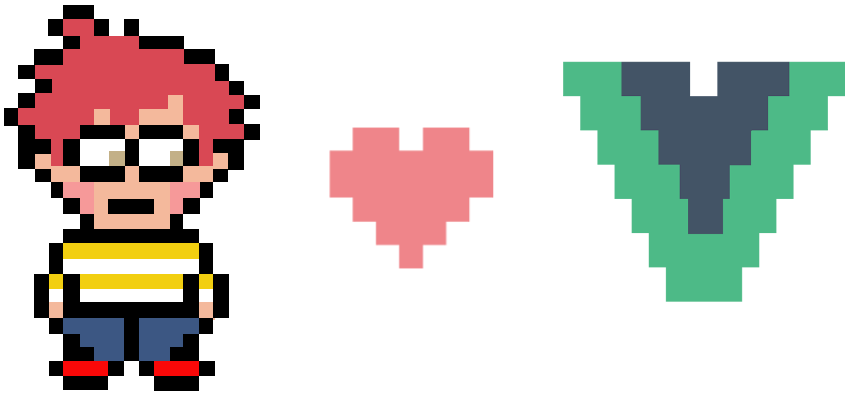完全版。愛知医科大学医学部の数学の対策方法の解説
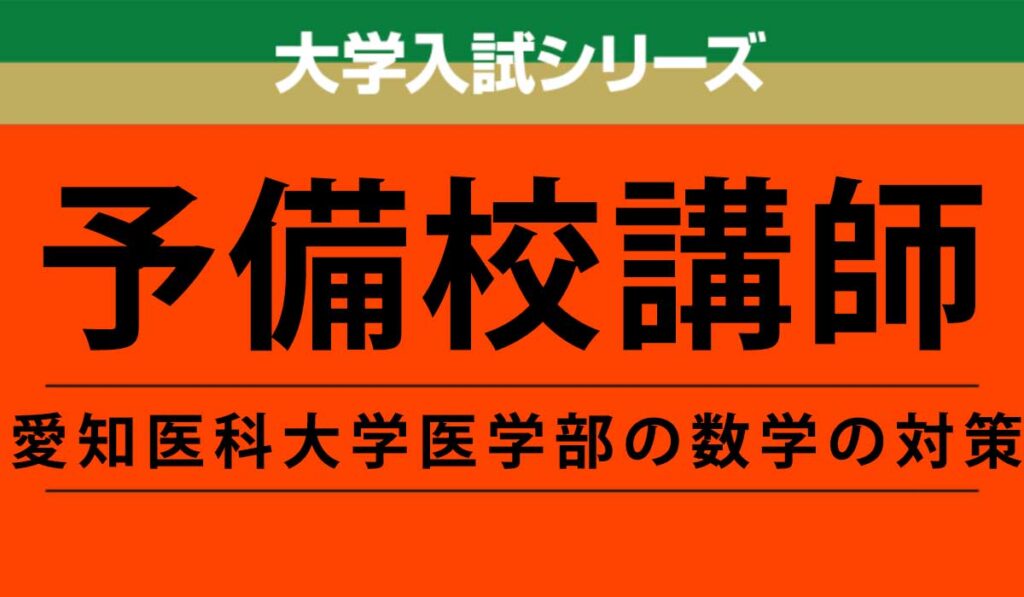
596 回閲覧されました
みなさんこんにちは、元予備校講師です。
医学部受験予備校に行ってなかったら表向きの情報しかネットにはないので対策のしようがないですよね。
医学部受験予備校に行ってても授業だけをして情報を教えてくれない先生もいますが。
情報は少しでも多い方がいいので愛知医科大学の対策方法の説明を私なりにします。
私は講師を辞めましたが講師をしていた時に生徒に伝えていた対策方法を解説します。
目次
愛知医科大学の問題構成
- 満点:150点
- 大問数:2014・2015年:5題、2016年・2017年:4題、2018年・2019年:3題
- 試験時間:2014・2015年:100分、2016年〜:80分
- 解答形式:2014・2015・2016年:全部記述、2017年〜:答えだけを書く問題と記述
- 大問の中の問題数:変動
問題の特徴
2014年〜2016年と2017年〜2019年で問題の傾向が変わっているので問題作成者が変わっていると思います。
それか問題作成者はずっと同じで何年ごとかに問題の感じを変えているかもしれません。
まず2014年〜2016年の説明からします。
2014年・2015年:大問1、2、3、4、5で全部が記述
2016年・2017年:大問1、2、3、4で全部が記述
2017年〜2019年と比べて難しいです、ガッチリ考えないと解けない問題が結構あります。
時間が足りないので途中まで解いて次の大問に移らないといけない時があったはずです、、
全科目合計の合格最低点は↓の通りです。
- 2013年:55%
- 2014年:61%
- 2015年:61%
- 2016年:52%
- 2017年:57%
- 2018年:61%
- 2019年:52%
解けないといけない問題があるのですがそれを解ければ合格点になるはずです。
捨ててもいい問題は明らかに「これは解くのが無理じゃ」って思う問題です。
次に2018年、2019年の問題の説明をします。
大問1が小問集合で大問2、3が記述です。
黄色チャートのEXERCISE、Focus Goldなら星4(一部解けなくてもいい問題がある)までバッチリ解ければ問題なく合格点が取れます。
凄く考えないといけない問題が少ないと思います。
大問2、3の記述に部分点はあるはずですが採点者の判断に任せると採点に時間がかかり過ぎるのでここまで合ってたら何点みたいな採点の基準があるはずです。
解答用紙の式変形を細かく見ると時間がかかるのでそこまで細かく見てないはずです。
過去の問題を見て思ったのは解き方が知られているけど最近どこの大学でも見てないのを一回だけ復活させてもう出ない問題があるということです。
生徒に何となくこの問題が出ると言ったのですが的中しました。
問題を解く時に考える練習をしないといけないのですがFocus Goldがお勧めです。
次は2019年の問題の難易度の分析です。
2019年の問題の難易度の分析
大問1
1)は数と式と数列を合わせた問題が出題されましたが簡単なので全部解いた方がいいです。
2)は因数分解と相反方程式みたいな問題が出題されましたが解くのは問題ないと思います。
3)はトーナメントの確率で答えだけを見ればシンプルな解答ですが解き方が思いつかなかったら捨てても大丈夫でした。
大問2
数学Ⅱの定積分がメインの問題ですが簡単なので全部解いた方がいいです。
大問3
二次曲線の問題で3)が時間的に解かないか解ける所まで解答を書くので問題ないと思います、難しいと思います。
総評価
2018年までで合格最低点が一番高くて61%なので解けないといけない問題が解ければ合格になるはずです。
2019年だと大問1 3)が捨ててよくて大問3(3)は解ける所まで解けば数学は絶対に合格点です。
2020年の問題の予想
2017年、2018年、2019年が難易度が安定しているので2020年も同じ感じな気がします。
データの分析、条件付き確率がまだ出題されていないので警戒した方がいいです。
何となくですが関数列の問題が出るかもしれません。
それとこれも怪しい感じがします。
関数方程式の恒等式型です、黄色チャートⅢのEXERCISEに載っています。
全国の大学で出題率がかなり下がっているので出てもいいんじゃないかと思っています。
最近佐賀大学の医学部で出題されています。
次は必要な得点率の説明です。
浪人に寛容か?
多浪が嫌いです。
4浪以上は親が愛知医科大学出身じゃない限り受けない方がいいです。
親がそこの大学出身なら多浪でも通る可能性がありますが高得点を取らないといけないです。
補欠合格で繰り上がった人を私の生徒で見たことはありません。
次はどの順番に問題を解くかと時間配分です。
どの順番に問題を解くかと時間配分
塾や予備校に行ってない高校生や集団授業を受けている浪人生は問題を解く時に最初から解いてないでしょうか?
もししてたらよくないやり方です。
理由は入試の問題でよく知られている解き方だけど試験時間的に解かない方がよかったりやたら複雑な問題は捨てないと試験時間内に合格点を取れなくなるからです。
愛知医科大学は大問1が小問集合なのでこの色合いが強いです。
最初から捨てる問題の時もあります。
最初から解いていきなり捨てる問題だったら解くのが大変だったり解けなくて凄く焦るはずです。
その状態で問題を解けても解けなくてももやもやした状態で次の問題を解いて冷静な状態で解けるでしょうか?
恐らく無理でしょう。
だから問題を解くときはこうしましょう。
自分にとって解きやすいかもと思う問題から解くといいです。
そうすると気持ちが落ち着いて問題を解くことができて試験時間が終わり合格点を取ることができることができるかもしれません。
私が最初に解かない方がいいと思う分野は整数問題、図形問題、確率、場合の数、データの分析などの思いつかないと解けない分野です。
理由は試験の開始直後は緊張しているので思いつかないかもしれないからです。
大問1は小問集合なので分からないと思ったら迷わず捨てましょう。
大問2、3は例えば大問2で(1)〜(4)まであったら(4)はひとまず解かず別の大問の(1)を解きましょう。
理由は(1)の方が(4)より簡単で得点率を上げるためです。
大問2、3問題を解いている際にどう解くかが分からなくなったらそれはひとまずおいておいて次の大問に移りましょう。
人間の脳は見る回数を増やすと頭の中で情報が整理されるので次見た時に問題の解き方が思いつくかもしれないからです。
ちなみに見直しの時間はないです。
大学の過去問を使って問題の解き方の練習をしないといけない
捨てる問題を見極める練習や解答の書き方の練習は過去問を使ってすれば実戦形式なので効果的です。
捨てる問題を見極めるのはどの大学も共通で解答を省くのは記述の大学で有効です。
捨てる問題を見極める練習は必ずしましょう。
本来なら捨てるべき問題を捨てずに無理に解こうとすると試験時間が足りなくなって合格点が取れなくなるかもしれません。
以下の大学の過去問を使って練習するのをお勧めします。
問題が変に難しすぎる大学は省きます。
愛知医科大学は記述もあるので記述が出題される大学も含んでいます、対策の記事のリンクもありますのでよかったらご覧ください。
- 聖マリアンナ医科大学
- 愛知医科大学
- 佐賀大学(医学部)
- 鳥取大学(医学部)
です。
練習している時に合格最低点の%を取れなくても諦めては駄目です。
本番では自分に合った問題が出題されて合格最低点を超える人がいます。
こういう生徒を私は何人も見ています。